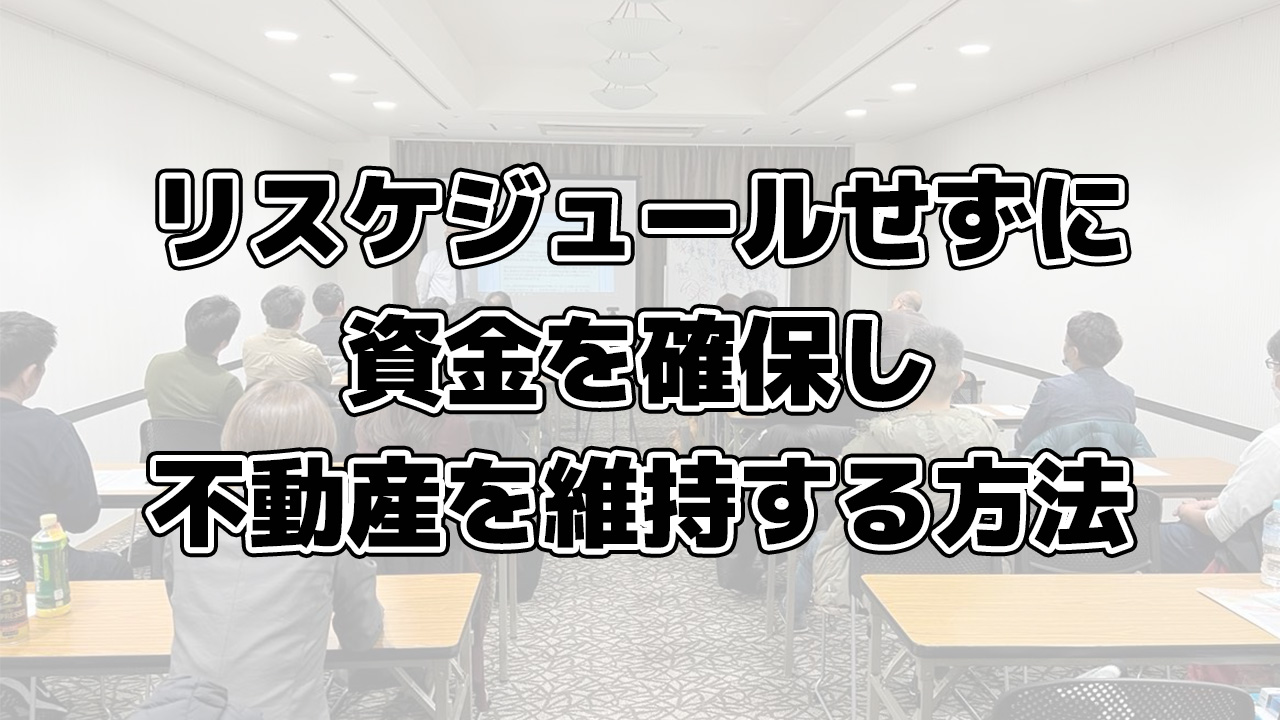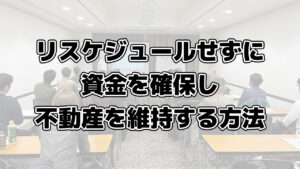たちばなです。
さすがに9月に入りまして・・・朝夕はいくらか涼しくなったように感じる新潟県見附市です。アナタの街はいかがでしょうか?
先日、9月8日に山形県米沢市を訪ねて来ました。Aさん50代男性のクライアントさんです。
この度、新規にご成約頂き・・・
「たちばなスキームを実行するにあたり、家族とのコンセンサスを得ておきたい。米沢までお出かけ下さらんか?」
と言うご意向を頂戴し現地へ出かけた、というワケです。
Aさんは
「息子に会社を継がせたいと思ってはいるのだが、懸命に手伝ってくれる息子に負債を合わせて会社継がせるのは忍びない。」
と言うご意向
奥さんは
「息子が何しようと自由。夫の事業を継ごうが、継がなかろうが、息子の意思を尊重したい。夫の作った負債を息子に継がせるのはまことに不本意。また住宅には自分自身は執着心強くないが、近隣に住む高齢の母に心配かけるのも不本意、母の存命中はどうにかならないか?」
息子さんは
事業をつごうか?やめようか?まだ結論は出ていない様子で、多くを語りはしませんでした。
会議では・・・
会社を継がせようとすると会社の負債も継承者は引き継ぐことになります。
会社を継がずに事業を継ぐ、と言う発想を持ち、その為の推進をワタシがサポートしつつ、いずれ訪れるであろう息子さんの「決断の時」を待とう、と言う話になりました。
不動産については・・・
「どうにか維持できませんか?」とワタシに質問下さったので、
「不動産が維持できるか?出来ないか?はワタシが頑張るのではなくて、Aさん一家が頑張れば維持できるでしょうし、頑張りが足りなければ維持は出来ないでしょう。」とお答えしました。
まず、そもそも不動産を維持する為に絶対的に必要なものは「資金」です。
これが用意できるか?出来ないか?これにかかっています。
不動産の維持についてはいくつか手法がある事はワタシも不動産のブレインとの日常的なコミュニケーションによって理解しています。
いくつかの代表的な維持方法についてChatGPTを使って解説して参ります。
?不動産のリースバックについて解説してください
不動産のリースバックは、資産を現金化しつつ住み慣れた家に住み続けられる柔軟な手法として注目されています。以下にその仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
? リースバックとは?
リースバックとは、自宅などの不動産を売却した後、買主(通常は不動産会社)と賃貸契約を結び、引き続きその物件に住み続ける仕組みです。英語では「Sale and Leaseback」とも呼ばれます2。
? メリット
住み慣れた家に住み続けられる 引越しの手間や費用が不要。通勤・通学にも影響なし2。
まとまった資金を一括で確保できる 売却代金は一括で受け取れるため、老後資金や事業資金などに活用可能。
固定資産税などの維持費が不要になる 所有権が移るため、税金や修繕費などの負担がなくなる3。
相続手続きが簡素化できる 不動産を現金化することで、相続人間の分割が容易になる。
周囲に知られずに現金化できる 売却情報が公開されないため、近隣に知られる心配が少ない。
?? デメリット
売却価格が市場価格より低くなる傾向 業者がリスクを負うため、相場より安く買い取られることが多い3。
家賃が高めに設定されることがある 売却後は賃貸契約となるため、家賃負担が増える可能性あり。
リフォームや建て替えが自由にできない 所有権がないため、改修には許可が必要。
契約形態によっては退去の可能性も 定期借家契約の場合、契約満了後に再契約できないこともある。
? 向いている人
住宅ローンの返済が困難な人
老後資金を確保したいが住み慣れた家を離れたくない人
相続対策として不動産を現金化したい人3
②不動産のリバーズモーゲージついて解説してください
もちろんです。不動産のリバースモーゲージ(Reverse Mortgage)は、特に高齢者向けの資産活用手段として注目されている金融商品です。以下にその仕組みと特徴をわかりやすく解説します。
? リバースモーゲージとは?
リバースモーゲージは、自宅などの不動産を担保にして、金融機関から生活資金などを借り入れる仕組みです。通常の住宅ローンとは逆で、毎月の返済は不要であり、借入金の返済は契約者の死亡後や物件売却時に行われます2。
? 仕組みのポイント
対象者:主に50歳以上の高齢者(金融機関によって異なる)
担保:持ち家(戸建てが主流、マンションは制限あり)
返済方法:
生存中は利息のみを返済
死亡後に物件を売却して元本と利息を一括返済
契約形態:
リコース型:債務が相続人に引き継がれる
ノンリコース型:債務が相続人に引き継がれない(ただし金利が高め)
? メリット
自宅に住み続けながら資金調達が可能
毎月の返済負担が軽減(利息のみ)
老後の生活資金、医療費、介護費などに活用できる
相続人がいない場合でも資産を有効活用できる3
?? デメリット・注意点
契約者死亡後、配偶者が住み続けられない可能性がある
不動産価格の下落で担保価値が不足すると追加返済が必要になることも
長寿化により利息支払い期間が延びるリスク
借入金額に上限があり、希望額に届かない場合もある
金利は変動型が多く、将来的に返済額が増える可能性あり3
? こんな人におすすめ
年金だけでは生活が不安な方
自宅を手放さずに資金を得たい方
相続よりも自分の生活を優先したい方
老後の医療・介護費用を確保したい方
③不動産の親族間売買について解説してください
不動産の親族間売買は、親子や兄弟姉妹などの親族同士で不動産を売買する取引形態で、通常の売買とは異なる注意点が多数あります。以下にその概要をわかりやすく解説します。
? 親族間売買とは?
定義:民法上の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族、配偶者)を中心に、親しい親戚間で行われる不動産売買。
利用される場面:
親が子に自宅を譲りたい
親族の住宅ローンを肩代わりしたい
相続による不動産の共有を解消したい2
? メリット
柔軟な条件設定:価格や支払い方法を自由に決められる
仲介手数料不要:不動産会社を介さずに取引可能
買主探し不要:親族間で話がつけばすぐに売買できる
愛着ある家を他人に渡さずに済む
分割払いも可能:親族間なら一括払いでなくても対応しやすい3
?? デメリット・注意点
みなし贈与のリスク:
市場価格より著しく安い価格で売買すると、差額が贈与とみなされ贈与税が課される可能性あり
一般的には「時価の80%未満」が目安とされる
住宅ローンが使いにくい:
金融機関が不正利用を警戒し、融資を断られることが多い
税制上の特例が使えないことも:
例えば「3,000万円の特別控除」などが適用されないケースがある
契約書の作成が必須:
口約束ではなく、正式な売買契約書を作成する必要がある
相続人の同意が必要な場合もある:
特に共有名義の不動産を売買する場合は注意
? 手続きの流れと費用
売買契約書の作成
登記申請(司法書士に依頼するのが一般的)
税務申告(贈与税や譲渡所得税の確認)
必要書類の準備(印鑑証明書、登記簿謄本など)
**費用の支払い(登録免許税、司法書士報酬など)
親族間売買は、信頼関係があるからこそ柔軟に進められる一方で、税務や契約の面では慎重な対応が求められます。特に「みなし贈与」や住宅ローンの問題は見落としがちなので、専門家への相談を強くおすすめします。
④不動産のオシドリ贈与について解説してください
もちろんです。不動産の「オシドリ贈与」とは、正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度で、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産を贈与する際に贈与税が大幅に軽減される特例です。以下に詳しく解説します。
? オシドリ贈与とは?
概要:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅などの居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
基礎控除との併用:贈与税の基礎控除(110万円)と併用可能なので、最大2,110万円まで非課税になります2。
? 適用要件
婚姻期間が20年以上
戸籍上の婚姻期間で判断。事実婚や内縁関係は対象外。
贈与対象が居住用不動産またはその取得資金
国内にある自宅が対象。別荘などは対象外。
居住要件
贈与を受けた翌年3月15日までに実際に居住し、継続して住む見込みがあること3。
? メリット
相続税対策:生前に財産を移転することで、将来の相続税負担を軽減できる。
持ち戻し不要:通常の贈与と異なり、相続時に財産を持ち戻して課税されることがない。
自宅売却時の節税:夫婦共有名義にすることで、譲渡所得控除(最大3,000万円)をそれぞれに適用可能。
配偶者の住居確保:相続トラブルを避け、配偶者の住まいを守る手段になる。
?? 注意点・デメリット
不動産取得税・登録免許税が高い:贈与による取得は相続より税負担が重くなる可能性あり。
贈与は一度限り:同じ配偶者からの贈与には一度しか適用できない。
贈与税申告が必要:非課税でも申告は必須。
相続税の配偶者控除との比較:相続時には1億6,000万円まで非課税になる制度もあるため、どちらが有利かはケースによる3。
? こんな人に向いています
将来、自宅を売却する予定がある
配偶者に住居を確保しておきたい
財産の偏りが大きく、相続税対策をしたい
⑤不動産の三為取引について解説してください
不動産の「三為(さんため)取引」とは、「第三者のためにする契約」に基づく不動産売買の手法で、通常の仲介とは異なる構造を持つ契約形態です。以下にその仕組みやメリット・注意点をわかりやすく解説します。
?? 三為取引とは?
三為取引は、民法537条に定められた「第三者のためにする契約」に基づいて行われます。これは、売主(A)と三為業者(B)、三為業者(B)と買主(C)との間でそれぞれ売買契約を結び、最終的にAからCへ直接所有権を移転する仕組みです2。
? 契約と登記の流れ
A(売主)とB(三為業者)が売買契約を締結
BとC(買主)が売買契約を締結
所有権はAからCへ直接移転(中間省略登記)
この「中間省略登記」は原則禁止されていますが、三為契約のように法的要件を満たす場合は例外的に認められています。
? 三為取引のメリット
三為業者にとっての利点
登記費用や税金の削減:中間者であるBが登記されないため、登録免許税や不動産取得税が不要。
資金負担の軽減:買主からの支払いで売主への決済が可能なため、業者が資金を用意する必要がない。
在庫リスクなし:物件を一時的に保有しないため、売れ残りリスクがない。
?? 買主・売主の注意点
買主のリスク
価格の不透明性:売主の売却価格を知らされないため、割高で購入する可能性がある。
融資の制限:金融機関によっては三為契約への融資を断るケースもある。
本人確認の重要性:売主の身元確認が不十分だと、所有権移転に問題が生じる可能性がある。
売主のリスク
買主の情報が不明:直接契約しないため、最終的な買主の意図や資力が不明なまま取引が進むことがある。
? 仲介との違い
項目 三為契約 仲介契約
契約形態 売買契約(A⇔B⇔C) 媒介契約(A⇔仲介⇔C)
登記 A→Cへ直接移転 A→Cへ移転
業者の利益 売買差益 仲介手数料(上限あり)
価格の透明性 低い 高い
三為取引は、業者にとっては効率的でコスト削減につながる一方、買主・売主にとっては価格や契約の透明性に注意が必要です。利用する際は、契約内容を十分に理解し、司法書士など専門家の確認を得ることが重要です。
代表的な事例を5つほど上げさせて頂きましたが、「おカネのかからない手法」は何一つ存在しません。
全ての維持方法で「必ず資金は必要」と言う事です。
その資金をねん出するためにアナタ方は「売れ上げ伸ばして経費減らして」と資金をねん出しようとするのですが、それで作れないからこそ・・・たちばなはじめに行きついた。
借りたカネについて無理な返済を止めれば資金は少なからず捻出出来ます。
その浮いた分が一年か一年少々で不動産を維持するためのコストに見合うか?見合わないか?と言う事ですから、それは「当事者の資金捻出度合い次第」と言う事になります。
例えば・・・
①借入が一億円あったとして、通常の月額元利返済が100万円だったとするならば・・・
100万円の返済を止めれば、毎月100万円が浮く計算になります。
②借入が一億円あったとして、リスケジュールして月額の元利返済を20万円だったとするならば・・・
20万円の返済を止めれば毎月20万円が浮く計算になります。
ワタシは「不動産を維持するのには資金が必要」と言い続けているのですから、①のケースと②のケース・・・どちらが不動産を維持できる可能性が強いでしょうか?
というワタシの問いに、アナタは即座に「①の方が可能性が高い」と答えるでしょう。
そうなんです。不動産を維持したいと思うならリスケジュールをしてはいけない、と言う事です。
一般に、返済が出来なくなってから不動産が売りに出されて他者の手に渡るまで・・・
一次競売の一括競売でスムーズに売れたとしても一般住宅なら概ね一年。事業用地なら概ね一年半は要します。
この期間にリスケする前の返済原資を停止すれば・・・ソコソコの資金になるのではないでしょうか?
ともすると「自ら買い戻す」などと言う芸当もリスケジュール前なら現実味を帯びて来ます。
下記に、当方の不動産ブレインとのLINEのやり取りを貼り付けます。
ご参考にされて下さい。
~ この続きをみるには ~